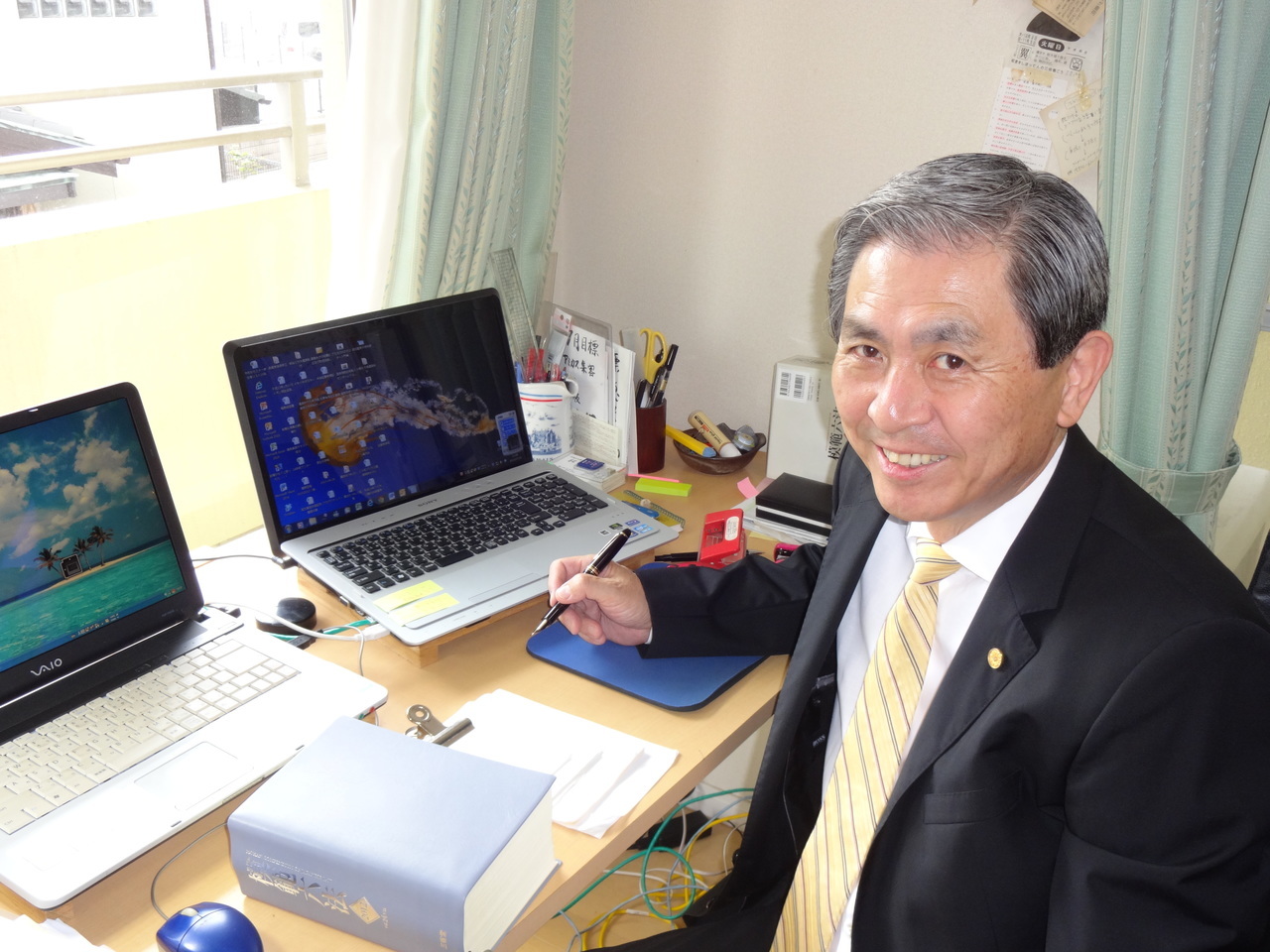受付時間
定休日:月曜
認知症による口座凍結の対処法と事前対策
認知症による口座凍結の対処法と事前対策

認知症による口座凍結の対処法と事前対策
口座凍結とは?
認知症になると、原則としてご本人およびご家族が銀行で預金を引き出せなくなります。預金に限らず、株式・投資信託の売買もできなくなります。
この金融機関の措置は、財産が事実上凍結されることから、一般に「口座凍結」と呼ばれています。
ご家族が介護費用や生活費を立て替えなければならないケースも多く、家計へ大きな影響を及ぼしますので、近年、認知症患者の急増を背景として、口座凍結の事前対策の重要性が叫ばれています。
口座凍結の事前対策
なぜ認知症になると口座凍結されるのか
金融機関が認知症になった方の口座を凍結するのは、その方の財産を保護することが目的です。
認知症で判断能力が低下すると、行おうとする取引がどういう効果を持つのかを理解できないまま実行・契約をしてしまったり、詐欺被害に遭いやすくなるリスクがあります。こうしたことを防ぐために、口座を凍結する措置を取るのです。
よくご家族からご指摘されるのは、「家族には銀行は預金の引き出しに応じてくれる」というものです。ご家族だからといって財産を適切に管理するとは限らず、残念ながら、認知症になったご本人の預金を身内が使い込む事態も聞かれます。そのため、金融機関は慎重な対応を取らざるを得ないのです。
口座凍結はいつからされるのか
1.ご家族が金融機関に伝えたとき
介護が始まると、経費の支払いをはじめ、金融取引をご家族に頼らざるを得なくなります。認知症になった方のご家族が本人に代わって金融機関で取引や手続きをしようとして、店頭でその旨を伝えたことを契機に、口座凍結されることがあります。
よく言われるのが、「窓口に行かずにATMでキャッシュカードを使って家族に引き出してもらうから心配ない」と考えていらっしゃる方がいます。高額な現金の引き出しに本人の意思確認が必要であったり、長期間の使用でキャッシュカードが割れたり暗証番号の誤入力で使えなくなったりすると、再発行でご本人の意思確認が必要となります。また、普通預金以外の金融取引の際にも、ご本人の意思確認が必要です。
2.金融機関に判断力が低下していると判断されたとき
認知症による記憶障害や判断能力の低下が原因で起こす次のような行動を、金融機関の窓口などで判断することがあります。
3.通帳、印鑑をよく紛失する。
同じ内容で何度も店舗に訪問する。同じ手続きを何度も照会する。
実際には起きていない行員の不正を主張する(「行員がお金を盗った」等)
4.認知症による口座凍結への対処法は?
➀成年後見制度(法定後見制度)
成年後見制度には、認知症発症前であれば任意に後見人を依頼できる任意後見制度と認知症発症後に家庭裁判所が後見人を専任する法定後見制度があります。
しかし、認知症などの判断能力の低下を原因として口座凍結されてしまうと、法定後見制度を利用することが唯一の対処法となります。
法定後見制度は、認知症など判断能力が不十分となった方を法的に保護・支援する制度です。預貯金や不動産などの財産管理、介護サービスや施設への入所に関する契約締結に関して、成年後見人からのサポートを受けられます。
ただ、法定後見制度の利用は、家庭裁判所への申立てが必要となります。申立てから利用開始まで数ヶ月かかるため、介護費用の支払いに間に合わない等の理由でご家族の立て替えが必要になることもあります。
また、成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、必ずご家族がなれるとは限りません。現状は親族が後見人に選任されるケースは全体の2割弱にとどまり、8割以上は、専門家等が選任されているのが実情です。
このほか、成年後見人に支払う費用の目安として、2万円以上が毎月の負担となることも認識しておく必要があります*報酬額は裁判官が事案ごとにふさわしい額を決めます。
法定後見制度の利用を開始するとその利用以降、継続して費用がかかることを覚悟しておく方が良いでしょう。一旦、法定後見が開始されると、裁判所が法定後見の利用停止を認めることは原則として高いハードルがあります。
後見の終了が認められるのは、ご本人の判断能力が成年後見制度による保護を要しない状態に回復した場合などに限定されます。
➁事後の対処では選択肢がない
認知症になり口座凍結されてしまった「後」の対処法は、成年後見制度の「法定後見制度」しかありません。ご家族ではない後見人に財産管理を任せざるを得ない場合があることや、専門家への費用負担が続くといった留意点があり、ご家族にとって使いづらい制度ということになります。
その影響なのか成年後見制度の利用は進んでいません。2020年で認知症患者数は推定で602万人とされていますが、成年後見制度の利用件数は2020年12月末時点で約23万件となっています。認知症患者数に占める割合としては3.8%と低水準です。
認知症による口座凍結への事前対策
事前に対策することのメリット
事前の対策で自分の希望を反映した財産管理が可能に
家族信託制度の利用
個人資産の多くを占める預貯金や不動産についてはどのような対策をすればよいのでしょうか。
「家族信託制度」の利用が考えられます。
テレビ番組で取り上げられたり、書籍が出版されたりしていますので、「家族信託」という言葉を目にされた方もいらっしゃるかと思います。
これは、専門家や法人でなく、ご家族に財産の管理や処分をする権限を託すことで財産管理を行う仕組みです。ご家族間で契約することから柔軟な設計が可能で、一般に「家族信託」と呼ばれています。
家族信託は自由度の高い制度です。例えば、成年後見制度では家庭裁判所が成年後見人(又は任意後見監督人)の選任をしますが、家族信託は委託者と受託者の契約で決められますので、ご家族以外の人物が介在せず委託者の想いに寄り添った財産管理が可能となるでしょう。
任意後見制度の利用
事前の対策としては、成年後見制度のうち「任意後見制度」も選択肢となります。
ご本人が契約した任意後見人に判断能力が低下した後、代わりにしてもらいたいことをあらかじめ契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
将来、ご本人の判断能力が低下したら、まず家庭裁判所に任意後見監督人の選任の手続きを行います。その上で、指定した任意後見人が任意後見監督人の監督の下に、定められた特定の法律行為(契約行為など)を本人に代わって行うことができます。
任意後見人をだれにするの財産管理等の内容を自由に決めることができる点が、「法定後見制度」との違いです。ただし、任意後見監督人の選任で家庭裁判所での手続きに日数を要することや、任意後見監督人の報酬がかかる点は法定後見制度と同様に注意が必要です。
任意後見制度は、事前対策ができる点で家族信託と比べられることもありますが、任意後見人は「身上監護」ができる点に大きな違いがあります。「身上監護」とは、ご本人の生活を維持するための仕事や療養看護に関する契約等のことをいい、例えば、介護施設の入所に必要な契約や、病院の入院手続き等がこれにあたります。
認知症とは

認知症になるとどうなる?
認知症とは
認知症の発症は身近なリスク
認知症は65歳以上の高齢者のうち認知症を発症している人は推計15%で、2012年時点で約462万人に上ることが厚生労働省研究班の調査で明らかになっています。認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の高齢者も約400万人いると推計されており、2060年には65歳以上の4人に1人が認知症とその"予備群"となる計算です。
「物忘れ」とは異なり、日常生活に支障
認知症とは、さまざま原因で脳の神経細胞が破壊され、日常生活を正常に送れない状況になることをいいます。加齢によるもの覚えの悪化「もの忘れ」とは異なります。認知症は症状が進行してくると、社会生活や日常生活に支障が発生してきます。
もの忘れと認知症の違い
老化によるもの忘れ 認知症
原因 脳の老化 認知機能の障害
記憶 体験したことの一部を忘れる
自覚 忘れたことの自覚はある 忘れたことの自覚はない
時間や場所 見当がつく 見当がつかない
症状の進行 あまり進行しない 徐々に進行
著しく進行することもある
日常生活 大きな支障はない 支障をきたす
75歳からが要注意
有病者の人口に占める割合を「有病率」といいますが、認知症の有病率は以下のように、75歳以降に急上昇するとみられています。
年齢階級別の推定認知症有病率のグラフ
75歳未満の認知症の有病率は、5%に満たない水準ですが、加齢とともに急上昇します。特に75歳を超えてからが注意したい時期です。
認知症の種類は?
認知症には、アルツハイマー型、レビー小体型、脳血管性、前頭側頭型と呼ばれる四大認知症があり、全体の60%以上をアルツハイマー型が占めます。
認知症の種類と特徴
認知症の種類により異なる特徴があるので、状況に合わせた治療、対策が必要となります。
四大認知症 それぞれの特徴
アルツハイマー型 脳血管性認知症 レビー小体型 前頭側頭葉変性症
脳の変化 脳の神経細胞が破壊され、脳が萎縮する 脳梗塞、脳出血などによって脳の一部が壊死してしまう 特殊なたんぱく質が脳の神経細胞に溜まり、脳細胞が死滅してしまう 大脳の前頭葉・側頭葉が委縮する
患者数 最も多い アルツハイマー型の次に多い 血管性認知症の次に多い 少ない
初期症状 もの忘れ もの忘れ 幻視、妄想、うつ状態、パーキンソン症状 身だしなみに無頓着になる、同じ言葉や動作を繰りかえす
特徴的な症状
認知機能障害(もの忘れ等)
もの盗られ妄想
徘徊
見当識障害(自分が今いる場所がわからない)
とりつくろい
など
手足のしびれ、麻痺
感情のコントロールがうまくいかない
など
認知機能障害(注意力・視力など)
幻視、妄想
パーキンソン症状
睡眠時の異常言動
自発性の低下
人格変化
よく行くお店で品物を持ち去る
仕事や家族、趣味などに興味を示さなくなる
症状の進行 記憶障害からはじまり、広範な障害へ徐々に広まる 原因となる疾患により異なるが、段階的に進行することが多い 調子がいい時と悪いときを繰り返し進行する ときに急速に進行することもある 進行はゆっくりで、年単位で進行する
久留米市・鳥栖市で相続対策

親の認知症にそなえた相続対策
認知症が進む前に対策をしておくことの重要性を理解いただくことで、自分たちに合った相続対策を選択できるかもしれません。
認知症になる前に行うべき相続対策
【認知症と判断された後では行えない相続対策】
遺言書
生前贈与
不動産の売買契約・賃貸借契約・請負契約
任意後見契約
信託契約
また、最も影響する事態として、預金口座の引落ができなくなります。金融機関は口座名義人が認知症であると判断すると、口座の不正使用などのトラブル防止のため口座を凍結します。
その結果、何も対策ができないまま相続を迎えることになるため、意思能力がまだあるうちに必要な対策を講じることが重要です。
【親が認知症と判断された結果起こる相続トラブル】
相続対策の効力を巡って相続人同士でもめる
親が望む財産承継ができない
相続税の節税対策ができない
介護費用や生活費、葬儀代を引き出せない
トラブル・リスクの例を見る
このようなトラブルを防ぐためには、まだ意思能力があるうちに対策しておく必要があり、かつ「意思能力があった」ことを証明できるようにしておくことも重要です。
これは、後になって他の相続人が「遺言を書いたときはすでに認知症だったから遺言は無効である」などと主張してくる可能性もあるためです。
親の認知症が進む前に取り組むべき相続対策
【認知症にそなえた相続対策の比較】
家族信託 遺言 生前贈与
認知症にそなえた相続対策として総合的に効果が高いのは家族信託なので、まずとりかかるとしたら家族信託がおすすめです。
認知症と判断される基準は?
認知症の症状がどの程度で意思能力がないと見なされるのかの基準ですが、認知症とひとくくりにされても、軽度だったり、日によって調子がいい時もあると思います。
たとえば、銀行などは下記のような行動ができない場合認知症と判断することがあります。
一人で窓口に来られるかどうか
氏名・生年月日を言えるかどうか
直筆で署名ができるかどうか
対応する各機関や法人によっても判断基準は多少異なりますが、担当者が本人と直接やり取りをして、総合的に意思能力の有無を確認します。金融機関では意思能力に問題ありと判断した場合、口座を凍結することがあります。
それでも〇〇にお困りなら
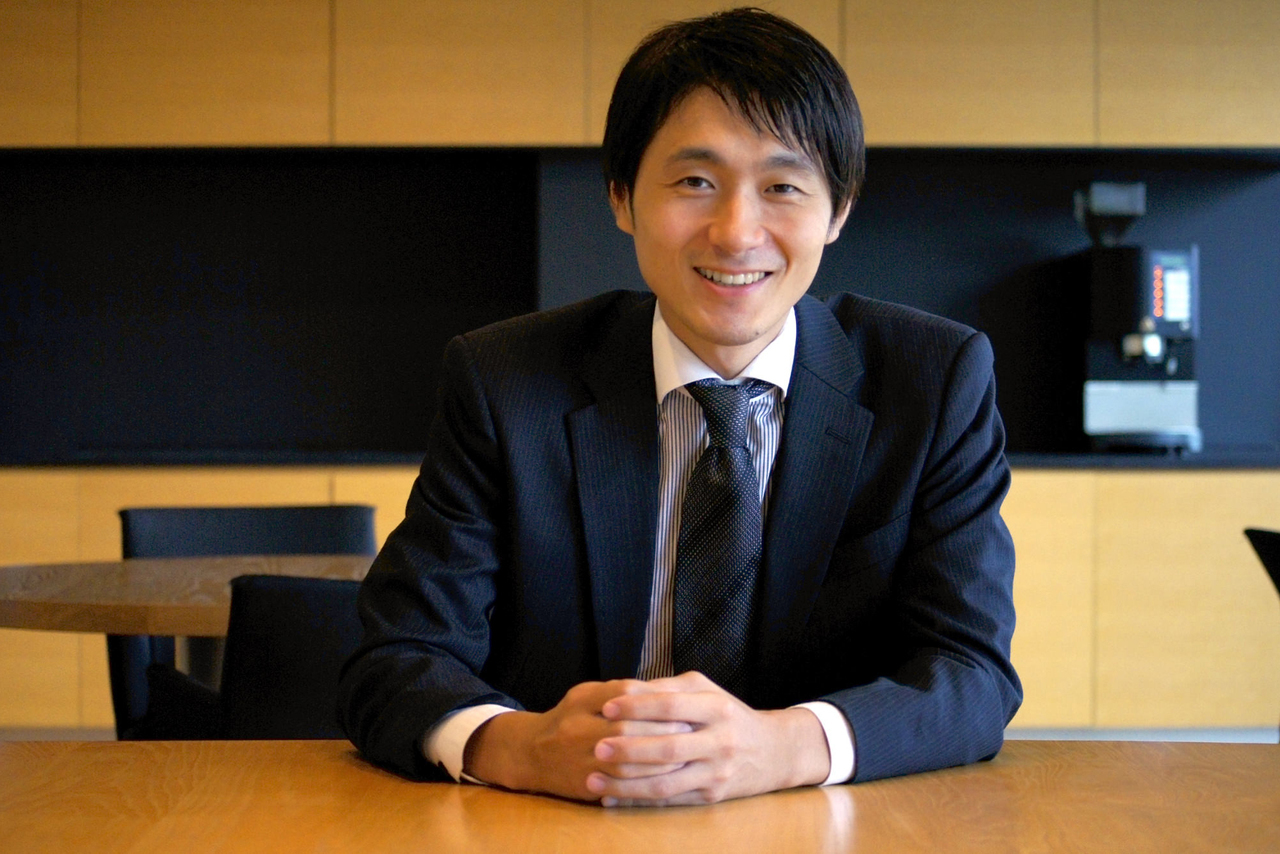
例)○○○代表の○○です。
あなたのお悩みを解決します!
※お役立ち情報ページに直接アクセスしてきた方へ、御社のサービスをご紹介してください。
この要素には、下記3点をご記入ください。
・ページ最上部で記載したお悩みやニーズを、御社のサービスでも解決できること
・そのお悩みを御社のサービスで解決できる根拠(理由)
・サービスの概要
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやエオカキクケコサシスセあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもや
※3点を読ませた後に、該当するサービスページへのリンクを張ってください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。