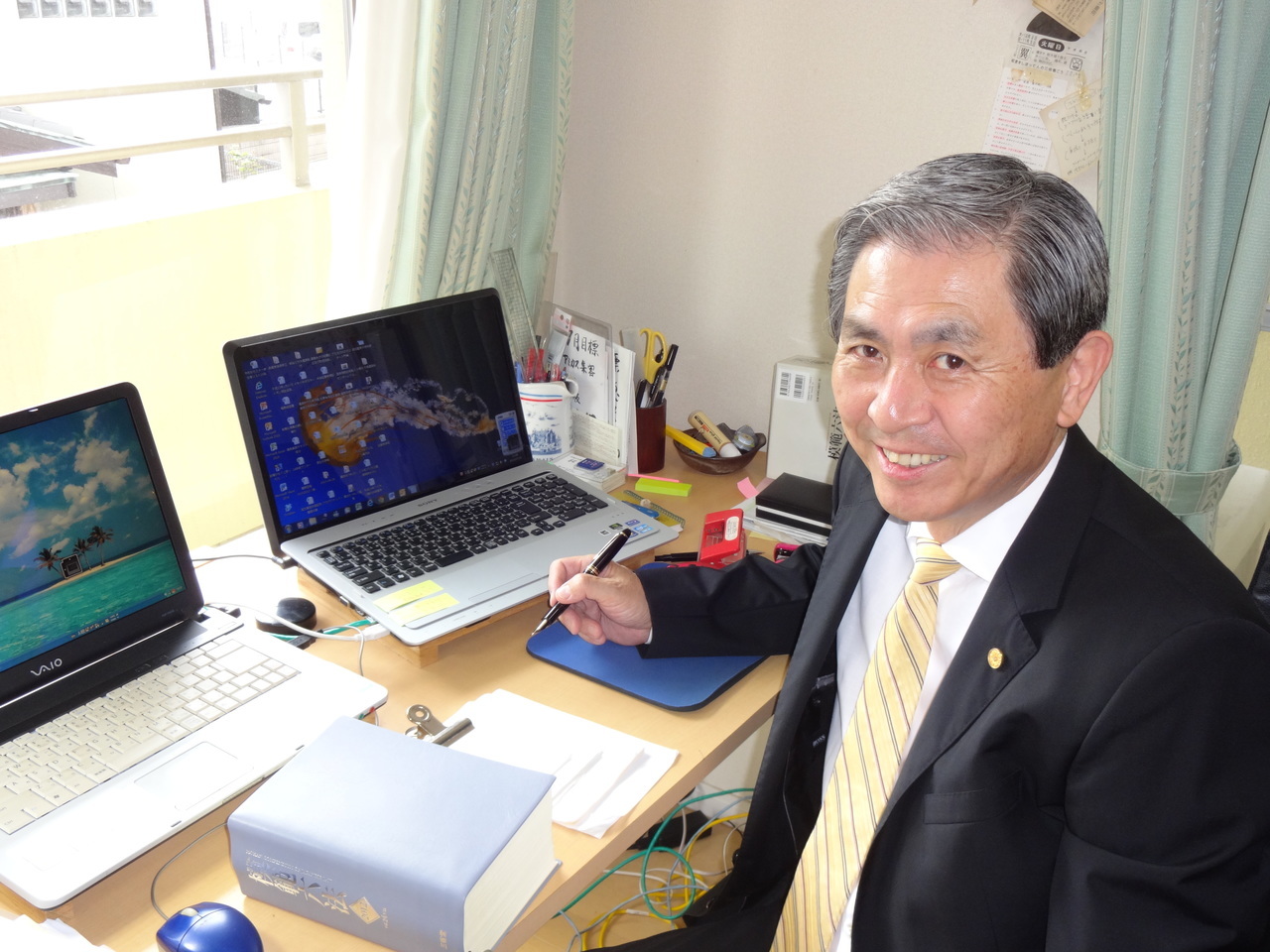受付時間
定休日:月曜
非協力な相続人の対処法
非協力な相続人の対処法

非協力な相続人の対処法
相続をめぐるトラブルがうまく進まず、まして家族どうしの仲が悪く疎遠であったりすると、相続人であっても連絡を拒否して話し合いをしない人もいます。連絡をしても手続きに応じない相続人がいる場合のどうすればよいのか対処法をお話しします。
なぜ、連絡を拒否する相続人が出るのでしょうか?
遺産がもらえる話合いをどうして拒否をする相続人がいるのでしょうか。
相続に対して協力しない態度をとるのか、その背景には、不信感があることが原因にあると思われます。また、トラブルになることを恐れて話し合いを拒否するケースもあります。相続では、次のような場合にトラブルが起こりがちで、家族の一部に対する不信感があったり、相続が新たに不信感を生じさせたりするきっかけになります。
【相続全般の問題】
1. 財産は自宅以外にない
2. 財産内容の種類が多く整理が難しい
3. 特定の相続人だけ故人を介護した
4. 特定の相続人だけ生前贈与されていた
5. 相続人に養子・前妻の子などがいる
6. 子供がいない(相続人は配偶者と兄弟姉妹)
7. 主張が極端な相続人がいる
話合いを拒否をする相続人も遺産分割協議対象者
遺言で遺産の分け方を定めていないと、相続人の間で遺産の分け方を話し合う必要があります。遺産分割協議といいます。
一部の相続人が連絡を無視していると、いつまでたっても遺産分割協議ができません。連絡を拒否する相続人だけを除いて話合いを進めたいところですが、一部の相続人を除いて遺産分割協議はできないのです。
一部の相続人を除いた遺産分割協議書ができても、預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)などの手続きに使えません。相続手続きでは遺産分割協議書のほか、故人(被相続人)と相続人全員の戸籍謄本が必要ですから、相続人が全員でないことはすぐにわかってしまいます。
相続の手続きを終わらせるには、相続の話合いを拒否する相続人にも応じてもらう必要があります。
非協力な相続人の対処法

拒否をする相続人についての対処法
相続人の中に連絡しても応えず中には拒否をしたりする相続人がいると、相続人のあいだで解決することは難しくなります。
だからといって、いきなり裁判所に調停の手続きをとることはおすすめしません。どうしても遺産分割が解決できない場合には調停手続きをとることになりますが、最初からとるべきではありません。まずは、第三者に入ってもらうなどして話し合いでの解決を図る方がいいでしょう。
ところが、早く相続の手続きを進めるため賛成している残りの相続人で遺産分割協議をして、連絡に応じない相続人に遺産分割協議の書面を送り付けてハンコを強要するケースもみられます。これは、相手に強引な印象を与えて争いが深刻になる恐れがあるので、このような強い方法は避ける方がいいでしょう。
最初にマイナスの点を伝える
まず、連絡に応じない相続人には丁寧に相続手続きに協力してもらうよう依頼します。電話、手紙、メールでも構いませんが、いきなりのアポ無し訪問は控えましょう。
連絡の内容は、ただ協力をお願いするだけではなく、手続きをせずに放っておくと起こる不利益があることを具体的に伝えましょう。例として、以下のような点を丁寧に伝えるとよいでしょう。
1. 死亡から、故人の借金があり3ヵ月を過ぎると相続放棄ができなくなり支払うことになる
2. 預金の引き出しや不動産の名義が変更できない
3. 相続税が高くなる
4. 裁判所で法的手続きをとると、お互いに面倒になる
話合いを拒否することで起こる不利益が相手に分かれば話し合いに応じるようになるでしょう。
しかし、遺産相続にまったく関心がない人にはあまり効果はないかもしれません。その場合は、相続放棄を提案して話し合いから外れてもらうようにしてもよいでしょう。
第三者に入ってもらう
連絡しても拒否されてどのような不利益があるかを伝えても連絡拒否や無視が続く場合には、第三者に入ってもらい解決を図ります。
相続人がお互いに会うことが嫌で連絡に応じない場合には、第三者が入ることで解決に向かうかもしれません。相続問題の専門の相続相談センターのが間に入ることで、話し合いに応じるようになるケースもあります。
しかし相続の専門家が入ると、すぐに裁判手続きをとると勘違いされて相手の態度が急変することもあります。そのような心配がある相手には、相続人でない親族や共通の知人など、相続に関係ない身近な人に間に入ってもらってもよいでしょう。
家庭裁判所の調停で解決する
間に入ってもらっても話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて、調停で解決を図ります。
ただし、遺産分割調停は家庭裁判所で話し合いをしますが、相手が出席しないなどの理由で調停が終わることも少なくありません。
調停で解決しない場合は「遺産分割審判」に移ります。遺産分割審判は、申立人と相手方の双方から事情や証拠をもとに、裁判官が遺産分割の方法を決定します。調停ではなく、相手が出席しなくても裁判官による審判が進められます。最終的には法定相続分で分けることになります。
審判が決着すると裁判所から審判書が送られてきます。審判は判決と同様の効力があり、遺産分割協議書がなくても審判書で手続きを始めることができます。
非協力な相続人の対処法

話合いを拒否すると問題が起きる
話合いを拒否しても相続手続きをそのまま放置しておくことはできません。相続手続き進めないと問題が起こります。相続手続きができない場合に起こる4つの問題は次のような事項です。
1. 相続放棄ができなくなる
相続放棄は、原則として死亡から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この期限を過ぎると相続放棄ができなくなってしまいます。
もしも、故人の借金を相続放棄をする必要がある場合は、連絡を拒否している相続人にもそのことを伝える必要があります。
この相続放棄は各相続人が個別に手続きをすることができますので、相続の話合いを拒否する相続人がいても他の相続人の手続きは止まりません。
2. 預金を引き出せない
故人の名義の預金は、金融機関に死亡を届け出ると入出金ができなくなります。これは、相続人による不正な引出しや遺産の横領を防ぐために行われるものです。
故人の預金を引き出すには、遺産分割協議が成立しているか、預金を引き出すことについて相続人全員で合意していることが必要です。相続人に連絡を拒否されて話し合いができなければ、故人の預金を引き出すことはできません。
ただし、2019年7月1日から遺産分割前の相続預金の払戻し制度が施行されて、相続人であれば単独で故人の預金を上限がありますができるようになりました。しかし、全額を引き出すには遺産分割協議が必要です。
3. 不動産を売却できない
不動産をはじめ故人の名義の遺産は、遺産分割協議で分割されるまで相続人全員の共有です。
売却される場合は共有者全員の同意が必要で、他の相続人と話し合いができなければ、不動産を売却することはできません。もちろん、実家の建て替えや増改築、賃貸なども同様です。
4. 税の申告に不利
もしも、相続税の申告が必要ならば、亡くなってから10ヵ月以内の手続きが必要になります。相続人全員の話合いができずに申告期限まで遺産分割協議ができない場合には、一旦法定相続分で相続税の申告をします。分割協議ができた後で、相続税の申告を再度することになります。
しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など相続税の特例が受けられません。なお一部については、手続きの適用を3年間延長することができます。
しかし、特例を受ける前の税額で相続税を納めなければなりません。相続税が増えるというマイナスは、話し合いに応じない相続人だけではなく相続人全員に及びます。遺産の額が多い場合には税金の負担も大きくなるため、できれば相続人の全員の納得ができるように遺産分割協議を成立させることは重要です。